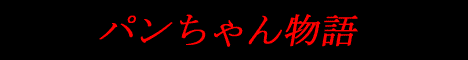これは某大手企業のneguro氏とバンコクでも有数の超高級クラブ ”ペガサス” のホステス、パンちゃんとの愛の物語です。パンちゃんのタイ女性独特の優しさと、neguro氏の文才を感じる見事な表現力に、この手の投稿文の好きなオレは感情移入してしまい、他人事なのに興奮してしまった。
これは某大手企業のneguro氏とバンコクでも有数の超高級クラブ ”ペガサス” のホステス、パンちゃんとの愛の物語です。パンちゃんのタイ女性独特の優しさと、neguro氏の文才を感じる見事な表現力に、この手の投稿文の好きなオレは感情移入してしまい、他人事なのに興奮してしまった。バンコクに出張できた日本人サラリーマンと高級クラブのホステス・・・二人の愛の軌跡を追ってみましょう。
第一話 ~出会い~
50人近くは居ようかというSとA~Cにクラス分けされた女性達の真っ只中、ママさんに早く選んでと促され、では英語の出来る女性をとリクエストして手を挙げた中に彼女はいた。 茶色に染められた長い髪、痩せすぎず太りすぎず、大きな胸をノースリーブの緑のロングドレスに包み、彼女は立ち上がりこちらへやってきて“サワッディ・カー”とお決まりの挨拶。
数時間後、常宿へ彼女を誘い二人でベッドに腰掛けて色々と話しをする。 幸いな事に彼女は、本当に英語が達者で、コミュニケーションには特に問題が無く、片言の日本語も話すようであった。 ご存知の通りタイ人が英語を流暢に話せるには、それなりの教育を受けたか、そうでない場合は彼女の今までの人生でそれだけの語学力を身に付ける必然性があった、という事であるが、敢えてその理由に付いては聞かなかった。
お互いにシャワーを浴び終えバスタオルを巻いただけの格好で、ビールを飲みながら話しているのだが、話しは尽きない。 バンコック・ノイに住んでいる事や、姉妹が何人とかどうでもいい話が続く。 彼女にとっても、私はいつも通りの、彼女の上に自分の欲望をぶちまけていくだけのただの“お客さん”であったはずである、少なくともその時点までは。
どちらからともなく近づき、バスタオルをはずす。 小さい、と彼女ははにかんで笑っていたが、結構見事なバストで整形でないことも意外感をもった。 掌でその大きさを確かめながら、首筋から肩へと舌を這わせていくと、ぴくっと反応し切なげに頭をもたせ掛けて来る。 その舌先を徐々に、今手で弄んでいる部分へと移動させていくと、呻き声が上がるようになり、乳頭を転がす頃には息遣いも荒く彼女の両腕は私の首筋に固く巻き付けられてきた。
自分の太股辺りに感じる彼女の茂みの感触が、小刻みに擦り付けるように変化していくのを感じながら、指でそれを掻き分けるように確認していくと、既にそこは受け入れる態勢が整っており熱く潤っている。 まさにその部分を今度は舌で、という瞬間彼女の反応が他のタイの女性達とは少し違う事に気が付いた。 普通恥ずかしがったり、“チャカチー”などと拒否されたりする事が多いはずなのに、彼女の場合まるでそうなる事が解っていたかのように、腰を浮かせこちらがそれを行いやすい様に動いてくれる。 若干の違和感を感じたものの、扇情的な彼女の動きがそんなちんけな理性を吹き飛ばし、ややもすると動物的な匂いのするセックスに没頭していった。
二人で頂点に達した瞬間、セックス本来があるべき形で二人は繋がっており、私のモノは彼女の子宮の中でまだビクッビクッと脈動を続けていた。 大きく深呼吸を続けニッコリと微笑む彼女に対し、この類の商売を生業とする女性達が決してしない、してはならない事を彼女が私に対して受け入れてくれた事に、私は後悔の念より彼女を信じたい気持ちと感謝の気持ちで一杯だった...。 (続く)
第二話 ~きっかけ~
熟睡しているかに見えたが、バンコクにおいて春を鬻ぐ女性達の大部分がそうするように、パンちゃんも明け方5時頃にベッドから起き出しシャワーを浴びていた。 そのシャワーの音で目覚めた私は眠い目をこすりながらも、昨晩まだ彼女にお金を渡していなかった事を思い出しスーツのズボンから財布を探り当て、白い紙幣を三枚とタクシー代として500Btを抜き出して煙草をくゆらせながら、彼女がシャワールームから出てくるのを待っていた...。
“あら、ごめんなさい、起こしちゃった? 朝仕事あるんでしょ、寝てて良いわよ。 私は道が渋滞する前に帰らなきゃいけないから...。”
“昨日お金渡すの忘れてただろ、はいこれ。 と、あとタクシー代。”
“コップン マーク カー、 ......。”
“うん? どうした? チップ足りないかい?”
“ううん、そうじゃなくて...。 貴方今日は仕事何時に終わるの? もし貴方さえ良かったら、今日も会いに来て良い?”
“仕事は夕方には終わるけど...、でもペガサスはどうするんだい? あそこは俺みたいな出張者は一人じゃとても行けないよ。 ”
“いいの、今日は休む。 じゃあ私の携帯に仕事終わったら電話頂戴、いつでも待ってるから...。 はいこれ、私の番号。”
“わかった、じゃあ夕方電話するよ。 またあとで。”
日中仕事をしている最中も、昨晩の彼女との情事が頭にこびり付き年甲斐もなく夕方が待ち遠しかった。 朝方家に帰っていく時の彼女の格好は、白のタンクトップに黒のボトムで足元はサンダルという至って軽装で、背中の白さに茶色に染めたポニーテールの髪の毛が良く似合っていた。 一見MBK辺りにごく普通にいそうな娘だが、その大きく魅力的な目と、ややもすると官能的過ぎる身体の線が他の女達とは一線を画させていた。
最後のアポが終了するなり彼女の携帯に電話を入れる。 “アロー...”タイの人達特有のHelloの発音だ。 こちらが今仕事を終えて一旦ホテルへ帰る旨を告げると、是非一緒に夕食を取りたいと言う。 それでは、という事で彼女が食べたいという日本食へ行く事にし、7時にエラワンのそごう前で待ち合わせをする事にした。 そごうの地下にはレストランそごうという日本食レストランがあり、味はまずまずだが、値段もそれなりにする場所である。 ただし待ち合わせ場所として解りやすい事と、少しでも良いものを食べさせてあげたいという傲慢な心理が働き、彼女達が自腹で訪れる事はまず無いであろう場所を指定したのであった。
そして彼女はやって来た、20分遅れで。 中近東・アジアと駐在生活が長く所謂“暑い国の人達の時間に対する概念”が日本人のそれとは違い多分に曖昧である事を経験から学んでいた私にとっては、いまさら驚くほどのことでは無かったが、多少苛々はしていた。 しかし黒のワンピースに包まれた彼女が“ソォーリー”を繰り返す姿を見たとたん、いらついた気持ちなどどこかへ行ってしまった。 熱燗が飲みたいという彼女のリクエストで杯を傾けながらの食事は、どことなく滑稽であったかもしれない。 日本人の男とタイの女性が英語で会話しながら日本食をつまむというシチュエーションをご想像頂けるだろうか。 世の常で自分達が気にするほど周りは気にしていない、ということは充分有り得たが...。
食事をしながら私が気になっていることが一つ有った ――それはこのあと最後は当然ホテルへ一緒に帰ることになるのだろうが、その前にどこへ連れて行かれるのか、ということであった。 店を休ませているのだから当然それなりの対価は支払ってあげなければいけない事は承知していたし、もちろん彼女から誘ったから云々という子供騙しのような論理を振りかざす気は毛頭無かった。 ただ単にデパートでの買い物やディスコといった人が混雑する場所がいまだに好きになれないだけだ。 だらだらとデパートの売り場を見て回るなど苦痛以外の何者でもない。
食事が終わりムッとする外気の中へ出た後思い切って彼女に、この後どうしたいか、と切り出してみた。 パンちゃんは少し考えた後、ニッコリ笑いながら私の手を引いて、すぐ隣にあるピー(エラワンの角にあるピーは金運が良くなる効果が有るといわれ、台湾や香港など主に中華系のお参りする人達でいつも混雑している)へ連れて行き、一緒に願懸けをしようといった。 彼女達の収入から考えると供物の花や線香の値段は決して安くないはずだが、お母さんのためと言って真剣に祈っていた。 彼女に合わせてお祈りをする事に少なからず困惑を覚えたものの、その真摯な態度の前では私も見よう見まねでお祈りする振りを続けねばバチが当たるような気になり、形だけ彼女に合わせて成行きを見守っていた。
十五分ほどかけてお祈りを済ませた彼女を見つめていると、振り向きざまに“貴方昨日も遅かったし疲れてるんじゃない?”と優しい言葉を掛けてくる彼女。“いや、別に...、大丈夫。”という私の言葉が終わらないうちに、“そうだ! 一緒にマッサージ行きましょうよ、私の友達がエンペラーホテルのマッサージで働いているから、彼女とても上手よ”という意外な返事に私の浅はかな読みは完全に裏をかかれた。 当時はタイ女性のメンタリティに不慣れだった事も有るが、諦めたつもりで最悪の予想をしていた時に嬉しい誤算というのだろうか。 だが往々にしてそのような驚きは相手に対する好意へと変化し、そして相手のペースに嵌まっていく前兆である。 今振返ると、あの彼女の一言がこれ以降の私と彼女の三年に渡る交際を決定付けたと断定して良いだろう。
同室で手を繋ぎあっての二時間のマッサージを終えて外に出た時には既に深夜になっており、サトーン通りの常宿へ戻るタクシーの中で二人は今まで以上に寄り添って座り、運転手の目を盗んではバードキスを繰り返した。 彼女の髪、彼女の肩、彼女の胸...全てが恋しく思われ、抱きしめているだけで幸福感に浸る事ができた。 世の中全ての恋の始りは多かれ少なかれ、そうであるように...。 (続く)
第三話 ~しばしの別れ~
あの軽薄体文章で有名な椎名誠氏がある著書のなかで人の好き嫌いに付いて、「人間の好き嫌いは約5億個の二進法による判断要因によって瞬時に感覚的に決定されるらしい。 例えば、髪の毛の長さ=好き・嫌い、目の大きさ=好き・嫌い、といった具合で、その5億個の要因の1/2以上が瞬時に好きという判断を下せばその人に対し好意を持ち、それが5億個に近ければ一目惚れということになるのだろう。」と述べられていた。 私とパンちゃんの場合は、おそらくお互いに2/3以上くらいの要因が瞬時に好きと判断したのではないか?
夕暮れ時にドンムアン空港を飛び立った飛行機の窓からは、バンコクのそれとは打って変わって非常にのどかな風景が広がっている。 夜のタニヤやパッポン等の喧騒はこの風景を見ている限りとても思い浮かばない。 寝不足で臨んだ接待ゴルフを終えた足で空港に直行し帰りの飛行機に飛び乗ったため身体はぐったりと重く疲れ切っていたが、静かに上昇を続ける飛行機の中で、私は昨晩の事を考えていた…。
……私の顔に覆い被さっていたパンの唇は熱い吐息と共に、次第に首筋から肩、そして胸へと移動していき、そこでふと動きを止めた。 見ると彼女の大きな瞳がこちらをじっと見詰め私の反応を伺っている。 こういった仕種がごく自然に行えるという事、即ち相手の男が自分の愛撫に対しどのような反応をするかを確認する行動を彼女が取るという事は、彼女の豊富なセックス経験を想像させるに難くない。 そんな事を考えているのはおくびにも出さず、彼女を見詰め返し微笑みながら髪を撫でてやると、安心したようにまた私を喜ばせる為の作業に没頭していった。
彼女の乳房が膝の辺りに当たる感触が心地よい。 それが小さな上下動からやがて徐々に振幅が大きくなってくる頃には、彼女の口の中には屹立した私が包み込まれている。 彼女のスタイルは余り音を立てずにねっとりと舌をまとわり付かせてくる。 その頂点から陰茎の向こう側へゆっくりとゆっくりと降りて行き、やがて戻ってきてその紅い唇で全体を再度包み込む。 子供の頃にアイスキャンディーを食べた、あの要領だ。 緩慢だがじっくりと焦らすように楽しむ彼女の動きが、むしろ欲情を掻き立てる。 そしてまた…あの確認するような目付きが。 なおも続けようとする彼女を手で制し、今度は私の番だというサインを送る。 仰向けに態勢を入れ替えた彼女の上に覆い被さり、今度は彼女が私にしたのと同じ手順で舌を這わせていく。
微かに彼女の体臭がする部分へ一気に舌を突き立てると、"オーイ"という反応。 ほぼ大部分のタイ女性が上げるよがり声である。 彼女が幾つの時からそれを生業とし始めたかは知らないが、まだ娼婦特有の色には染まりきっていないその部分を丁寧に丁寧に愛撫していく。 最初の腰を浮かせる程度の動きとはうって変わって、今では充分に潤った谷間を私の顔に強く擦り付け激しく動かしている。 息遣いが荒くなっている彼女へ"You wanna come?"と聞いてやると"…yes、…YES! Make me come!"と言いながら、私の頭を掴んで一層強く股間を押し付けてくる。 太股を大きく開かせた状態で花芯の部分を舌で小刻みに振動させてやっていると、間もなくその口から漏れていた"オーイ"の間隔が短く鋭くなり全身が突っ張ったかと思うと、やがて私の頭を掴んでいた両腕の力が抜けた…。
彼女が脱力している間に私も態勢を入れ替え、既に受け入れ準備が整い過ぎるほど整っているその部分へ割って入っていく。 私のものが挿入された瞬間、ビクッと彼女は軽い痙攣をし、この後にくる先程より更に大きな快感の波に身を委ねる用意をする。 しばらく軽い反復運動を行った後彼女の上体を起こさせ、丁度私が胡座をかいた上に座らせるような格好の体位に変えると、より深く挿入されたようで口元がややもすると半開きになり、またぞろ腰の動きが激しくなってくる。 男は一回射精してしまえば後は萎えて行くだけだが、女は違う。 一度その気になれば続けて何度でもいく事ができるという。 羨ましい限りだ。 動き続ける彼女の腰の振動によって引き起こされる微妙な振動の快感が身体中に広がったと思った時、私も彼女の中に果てた。
”パンちゃん…、こんな事聞いて申し訳ないんだけど、普通貴方達はお客さんに絶対コンドーム付けさせるでしょう。 逆にコンドームを付けないセックスなんて貴方達には有り得ないはずだけど…。 どうして?""貴方は…、最初から優しかったから…。 他のお客さんと違って乱暴にしたりしないで私を大事に扱ってくれる。 そりゃ私だって自分のビジネスが何かくらい解ってるし、奇麗事を言おうなんて思わない。 ただ、私を一晩のパートナーとして選んだのなら、パートナーとして扱って欲しい。 確かに私の身体はお金で買われたのだから、お客さんが喜ぶように多少の事は我慢するけど…。 でも私をモノのように扱う人達は嫌い! そう…、貴方が優しくしてくれたから…、貴方とのセックスは本当に気持ちが良い。 有り難う…。"
結局二人とも昨晩は殆ど睡眠を取らずにその様な会話を明け方まで続けた。 接待ゴルフに行く為に私は5時には起きて準備をしなければならず、身体はしんどいものが有ったが。 別れ際パンちゃんは私が今度いつバンコクに戻ってくるかをしきりに尋ね、出来れば毎日電話をして欲しいと言った。 恋愛は障害が多い方が熱く燃え上がるというが、果たしてこの遠距離恋愛はどう進展するのだろうか? パンに対しての熱い思いを抱く自分とそれを冷静に観察する自分が交錯し、機上で私はそのまま眠りに落ちて行った…。 (続く)
第四話 ~遠く離れて~
ふと時計を見ると午後3時過ぎになっている。 彼女に電話する時間である。 同僚に外で煙草を吸ってくると言い残し、オフィスの外へ出る。 エレベーターを降りビルの外に出た所で携帯のスイッチをオンにし煙草を咥えて火を付け、おもむろに "001-661-8XX-XXXX" とダイヤルする。 パンの携帯電話だ。 夜の仕事のせいで彼女が起きてくるのは早くても午後の2時過ぎで、遅いと本当に夕方近くなる時もある。 時差の為バンコクは今2時を回った所で、そろそろ彼女も起き出している時間である。 やや低めの長い呼び出し音が"プーッ"と鳴り電話がかかった。 今日は一発でかかったから良かったものの、必ずしも通信状態が良くないタイでは辛抱強く何度もかけ直さないとならないし、通話中に"ブツッ"といきなり切れる事も少なくない。
"アロー…"
"パンちゃん? How are you!"
"△△△?! I miss you!"
今にして思えば、この "I miss you" こそ私が一番失敗したと思っている言葉だ。 私はその字面通りに受け取っていたが、タイの言葉に直すと "キットゥーン"、即ち "愛している" という意味になる事を当時私は知らなかった。 いくら流暢に話すとはいえ彼女にとっては日常生活において使用頻度が低いであろう事を考慮してあげなければいけなかったのだろうし、英語に対する理解度の違いをもっと推し量ってやらねばならなかったのに。 最初の内は良かったがこの微妙なニュアンスの違いが、時間が経つに連れ後に大きな波となっていったのかも知れない。
毎日5~10分程度の簡単な愛の交歓。 おそらく端から冷静に観察すれば本当に下らない会話であったかもしれない。 今何している(電話しているに決まってるだろ!)、 昨日は遅かったか(夜の商売だから遅いのは当たり前)、 バンコクは暑いか(愚問)などなど…。 本当にどうでも良い会話がだらだらと続く。 しかし、そういった事に対し当事者同士が不思議と変に感じない、というのが恋愛の凄い所である。 まぁ私の場合幸いだったのは、ここは日本ではないので英語で話していても胡散臭い目で見られないで済む、という事だった。 実際出張などで日本へ行った際に、携帯電話を使って英語で会話していると "何なの?、この人" という目で見られる事が多く、特に公共の場で話をしなければいけない場合には、相当気を遣う。 日本は排他的な国と言われる事を実感する瞬間である。
時々、仕事が立て込んで遅くなり夜などに電話するとエライ目に会う。つまり彼女が夕方から友達と集まって酒盛りをしている時に出くわすと最悪である。 (パンは完璧に "キーマオ" 状態を決めると頑固で手が付けられなくなる女だったので、なるべく彼女が酔っ払っている時に電話するのは避けたかったのだが、逆に電話をしないと翌日たいそう不機嫌で、浮気をしていたのではないかと疑われ、下らない言い訳をだらだらと小一時間も繰り返したりした事も有った。) 酔って電話口で "大きな声で私を愛してると言って" などとほざかれた日には携帯電話を叩き付けたくなることもしばしばで、街中などでこちらが恥ずかしがって小声で囁こうものなら "え? 聞こえない、私を愛してないのねっ!" と返し技を決められ、最後は本当の大声で叫ばなければならない羽目に陥るので、こういう時は観念して最初からある程度大きな声で "I love you!"と言ってやる方が被害は少ないという事を学習するにはかなり時間が掛かったし、相当こっ恥ずかしい思いもさせてもらった…。
またある時、彼女の携帯に何度電話しても通じない事が有った。 こうなると心配が心配を呼び居ても立っても居られなくなるものである。 仕方ないので、パンに教えてもらっていた自宅の電話番号にかけてみる。 数回の呼び出し音の後受話器を取る音が聞こえたので、良かったと思い "Hello、パンちゃん?" と言うと、 "………"と沈黙が続くだけ。 二度三度と繰り返してみても、やはり沈黙。 一瞬間違い電話をしたかと思い、一旦受話器を置いて確認しながら同じ番号を回すと、相手の反応はやはり "………"。 こちらもむっとしながらまた彼女の名前を口にした途端、"Pan… マーケット!" と女の声で言われガチャッと電話が切れたが、物足りないようなしかし何か安心したような気分に包まれた。 後日パンに聞いた所によると、電話に出たのは母親だが、母親も英語は話せないので何と言って良いか困って "パンは市場に買い物へ行った" とだけ言って電話を切ってしまったのだそうだ。 (だったら最初から家の電話だと誰も英語話さないからと説明しておけっての!) まあそんな感じで私から彼女へのラブコールは(本当に不思議な事だが)基本毎日続いた。 (続く)
第五話 ~再びバンコクへ~
①日本食またはタイ飯→②タニヤでカラオケ→③(時間・体力あれば)ラチャダーの風呂屋、というコース。
会社内では②までなら前菜コース、③まで行くとフルコース、と命名されていた。 パンちゃんは②のタニヤでカラオケまでは許容範囲内、しかし当然③はアウト!なので、(支店の人間が)③まで行きたそうな雰囲気の時は事前にカラオケの段階で、今日は長引いているが何時頃終わりそうだからその時に電話する/ホテルへ来てくれ、という連絡を入れておく。 この一本の電話の有無が後々明暗を分ける(彼女の機嫌の善し悪しに関わる)ので、これは絶対外せない。
フルコースに付き合った場合が一番苦労する訳だが、ホテルへ帰ってくると既に深夜の12時近く。 しかし証拠隠滅の為素早くシャワーを浴びて、風呂屋で付いた石鹸の香り及び泡姫の香水などもろもろの匂いを消し去る事に専念。 そして念を入れてホテル備え付けのボディローションなどを体中塗りたくり、パンちゃんの到着を待つ。 「シーザー」や「ホノルル」、「エマニュエル」といった風呂屋でかわいい泡姫にしっかり抜かれている事を見抜かれない為、君とヤリたくて仕方ないという風体で彼女と接し、努めて元気に振る舞う(こういう時、自分を含めて男って本当に馬鹿だな、と思う)。 但し、今日は付き合いでカラオケにずーっと居たので若干疲れた、という大嘘もジャブとしてかましておく事も忘れない。 そしてメインイベントに突入していく訳だが、ここからが一番大変な訳である。 ここ数年一度抜いてしまうと二回戦めの時に時々本人の意思とは裏腹に暴れん坊将軍がぐったりと倒れてそのまま昏睡してしまい、非常に焦る場合が出てきた(そろそろ紅い球が出るのか? 俺は打ち止めが近いのか?!)。当然不発は許されない状況であるから、暴れん坊将軍が気合十分の頃合いを上手く見計らってパンちゃんに突撃していく事になる。 人生三十余年にして初めて "義理マン" の意味と辛さを知ったバンコクであった。
約二ヶ月ぶりのバンコクは10月とはいえまだまだ暑い。 ドンムアン空港の到着ロビーを出てホテルのリムジンが配車されるのを待つ間、煙草をふかしながらバンコクに戻ってきた事を実感する。 ちょっと埃っぽい、何かを焼いているような煙の混じった空気がむしろ懐かしく感じられる。 白い帽子をかぶり制服をぴっちり着込んだリムジンの運転手が静かに車を発進させる。 しばらく走って高速に乗る頃、おもむろに携帯をオンにしてパンちゃんに電話する。
"パンちゃん? 今着いたよ。 これからホテルにチェックインするね。"
"わかった。 今日はどうするの? 私と会ってくれるの?"
"もちろん。 何食べたい?"
"う~ん、私は何でもいいけど…、△△△は?"
"そうねぇ、センミー・ナーム(汁そば)とか軽いものでいいけどね"
"じゃあ、これから私ホテルのロビーまで行くからそれから決めましょ。"
"わかった、大体7時くらいかな? 近くに来たら電話ちょうだい"
"オッケー、オッケー、See you!"
私の飛行機が着くのは大抵夕刻で、ホテルにチェックインするのが6時過ぎ。 彼女の家はバンコック・ノイなのでサトーン通りの私のホテルまではタクシーで下手すると一時間くらい掛かる。 それもこれも悪名高い渋滞の為だが、むしろ空港に迎えにこられたり、ホテルロビーで待っていられたりするより好都合かも知れない。 当然苛々はするが、待たせるより待つ方が気が楽というものだ。
やはり30分遅れるという連絡が有り、彼女が到着したのは7時半過ぎ。 このホテルはサトーン通りに面してはいるが、ホテル自体はやや奥まった所に位置しているため、非常に静かであり、全体的にシンメトリーでデザインされた内装がその落ち着いた雰囲気をより一層醸し出させる。 客層はビジネスマンが大半だが、日本人旅行客も多く中年夫婦やOLの二人・三人連れもよく見掛ける。 私はレセプション近くのカフェに座ってコーヒーを飲みながら彼女を待っていた。 タクシーから降りた彼女が微笑みながら近づいてきたので、本来なら抱きしめあったりキスしたりしたい所だが、私の顔を既に覚えているホテル従業員達の手前ここはぐっとこらえて、あくまでも久し振りに友人に会った、という風を装った。 後で冷静に考えてみれば、出張者がバンコクでミアノーイ(お妾さん)に久し振りに会ったというシチュエーションは歴然としていたので、そんな無理な繕い芝居をする必要も無かったな、と思うのだが…。
私が「紀伊国屋」で本を買いたかった事もあり、今晩は結局伊勢丹6階の「タンジン」で軽く食べる事にした。 (余談だがここに入っている「鎌倉屋」という日本のステーキ屋はランチに良く利用している。 もう少しボリュームがあると嬉しいが。) 「タンジン」はシーロムに本店があるタイ王宮料理の店で、全般的にそれ程辛さがキツくないのが特徴といえば特徴かもしれない。 タイの女性と食事すると、特に現地のものを食べに行くと感じる事は、本当に世話好きだな、という事である。 パンちゃんも例外ではなく、スープは飲みたいか、辛くても大丈夫か、この魚は美味しいから食べてみろ、もっと御飯頼むか、エトセトラ。 私は機内食を食べているのでそれほどお腹は空いてない、と言ったんだけどなあ。 こうなると悪い気がしてついつい食べ過ぎてしまう、とそれはそれで幸せなのだが。 小一時間ほどで死ぬほど腹を膨らましている私を見つめてニコニコしている彼女に、どうする? と聞くと、日本語を勉強したいので、本を買って欲しい、というリクエスト。 おっとでたか!って感じ。
この類の台詞はこの手の付き合いに慣れていない人にとって非常に危険な殺し文句であろう。 というのも、 "そうか、こいつ俺の為に日本語を勉強したいんだ、う~ん愛い奴愛い奴。" と我田引水な演繹思考を展開しがちだと思うし、実際その様に言われて舞い上がってしまった人達を何人も知っている。 彼女達にしてみれば(その時は多分本気でそう思っていたとしても)一時の熱病みたいなものだろうし、我々だってタイに初めて行ってタイ料理を食べたら "あ、結構いけるな、ちょっと病み付きになるかも" などと短絡的に考えてしまうのと似ている気がする。 だから、彼女達がこの手の台詞を考え無しに言い放ち、それを真に受けていつか失望を味わう男達がいるとしても、彼女達を責めてはいけないと思う。
好みの小説や週刊誌を選び出し、パンちゃんが自分で選んできた日泰・泰日辞書や決まり文句会話集などと合わせてレジに提出し、会計は約5,000バーツ。 海外では本自体も定価の2~3倍の値段である。 その金額自体は我々にとってはなんて事無い金額だが、5,000バーツ持ってパッポン辺りへ行けば何人ペイバーできるか。 こんな時に貨幣価値という事をしみじみ考えてしまう自分が時々嫌になる事もある。 もっと素直に色々楽しめたらいいのにな、とも思う。 パンちゃんのカバンに本を突っ込んでもらいながら、次はどこ行くの? と聞いてみる。 と今日は少しお酒を飲みに行きたいとの返事。 という訳で我々が向かったのはすぐ近くのエラワンハイアットにある「スパッソ」。 詳しくは外道さんの "クラブ・ディスコ(高級娼婦を求めて)" の項を御参照頂きたいが、当時(97年後半)はまだ最先端スポットであった事もあり、我々が10時頃行くとまさに芋洗い状態。 パンに手を引かれて何とかカウンターに席を陣取った。 (続く)
第六話 ~携帯電話~
"ここは良く来るの?"
"うん、たまに友達と。 でも少しの間音楽を聞いたりするだけね。"
"そうか、まあお洒落な感じの場所だけど、ちょっと煩いね。"
当時は此処が高級娼婦の溜まり場であることは知らなかったし、それを目的とした男達が集まってくる事など知る由もない。 しかしそれを知った後でも、(ペガサスを休んで)パンがここで小遣い稼ぎをしていたかどうかを詮索する気も無かったし、その必要も無かった。 世の中には、特に男女が付き合っていく上では知らない方が幸せな事も多く存在すると思う。 結局彼女はブランデーをストレートで三杯、私はウイスキーソーダを二杯とテキーラをショットグラスで三杯空けてほろ酔い加減となり、「スパッソ」を後にしホテルへ向かった。
ホテルへ着いた後も飲み足りないのか、彼女はミニバーからウイスキーの小瓶を取り出し、オンザロックにして飲み続ける。 私は身に付けていたスーツから携帯や煙草など小物類を取り出してソファー近くのテーブルの上に置きながら、元来酒が強い方ではないのでシンハ程度にして付き合う。 今日の彼女は襟元が大きく開いた形になっている黒いシャツに白の膝丈のボトムという至ってシンプルな格好。 指輪や腕輪などアクセサリー類を付ける事は余り好まなかったようで、首にいつもしていたお守り代わりの金のネックレス以外は見た事が無かったし、他のタイ女性達と違っておねだりされた事もなかった。
ビールを片手に私がソファーに座ると、彼女も隣に座り直してきた。 そしてキス。 ブランデーをかなり飲んでいるせいで酒臭い。 キスしているというより、その感触は濃い水割りの氷を口に含んだようだ。 その水割りの氷のようなものが段々と生暖かくなり、私の口の中で蠢く生き物に戻りつつあった時、彼女はおもむろに顔を離して聞いてきた。
"ねえ、お願いが有るんだけれど…。 聞いてくれる?"
私はやや身構えながらも務めて冷静に、そして明るく振る舞った。
"なんでしょうか? お嬢様。 私に出来る事であればなんでもどうぞ。"
"私が使っている携帯電話は古いモデルで、サイズも大きくとても使いづらいの。 よく故障するし、知ってるでしょう貴方も。 あなたが持っているそのMOTOROLAのSTARTAKは最新モデルで(97年当時)格好良いわ。 小さくて軽いしね。 ……ねえ、それを私にくれない?"
私は唖然とした。 何といっていいか解らずに即答できずに居た。 買ってくれというならまだしも、くれと言われても…。 当然携帯電話は商売の必需品であり、明日も使用する訳だ。 そもそも、この番号は私のであって、彼女のではない。 明日からの仕事に差し支える事は明白である。 御参考までに、アジア地域では日本と韓国を除けばシステムは一緒であり、転送サービスさえ申し込んでおけば、香港でもシンガポールでもタイでも、どこでも一つの電話機で事足りるのである。 当然の事ながら、パンちゃんには以上のような事を説明した上で、きっぱりと拒否した。
"どうして? あなたからの電話を待っているのは私なのよ! 私を愛していないの? 国際電話代だって馬鹿にならないでしょう、 私もお金無いし、助けてくれたって良いじゃない!"
前にも書いたが、彼女は酔うと自分の論理に執着し何があっても自説を曲げない傾向がある。 彼女にとっては、たかが携帯電話というモノひとつなのだが、私にとってもされど携帯電話なのだ。 この携帯を彼女にあげて新しい携帯を購入するまでに失われる、今後もたらされるであろう将来の情報・ビジネスチャンスといった機会損失は甚大なので、私としても"はいそうですか"と簡単に首を縦に振る訳にはいかなかったのである。 完璧にすねてしまい苛付きながらむこうを向いて酒をあおり続ける彼女に対し、私がオファーできる代替案は一つだけだった。
"パンちゃん、この携帯電話は今も言ったように仕事でどうしても必要だから、君にあげてしまう事はできない。 これは辛いけど、仕方ないことだから解ってね。 替りといっては何だけれど、今度タイに来る時に新しいSTARTAKを買ってきてあげるよ。 君専用の。 但し番号はパンちゃんが今まで使っていた番号をそのまま使って下さいね。 国際電話は…、もし緊急に連絡したい時はワンコールで切って、私が折り返しかければ君の負担は少ないでしょう。 これならどう?"
すでにトロンとした酔っ払いの目付きに変わってしまっているパンが、こちらを振り向いて少し考える仕種をした後で、もう一度説明して、と言ってきた。 酔っ払っているので、おそらく考えがまとめられないのだろう。 私が次回来る時に新しい携帯を買ってくる事などをもう一度ゆっくりと説明してあげると、今までの憂鬱そうな表情から一転満面の笑みを湛えて急に抱き着いてきた。 彼女の身体を抱きしめ返してやりながら、女性の涙に弱い自分を、馬鹿な奴、まだまだ甘いな、と客観的に見つめていた。
赴任地へ戻った私は、約75,000円相当するチャーコールグレー色の新品STARTAKを買いに走ったのだった…。 (続く)
第七話 ~転機~
パンとの一向に要領を得ない会話に私はイラつき始めていたようだ。 テーマは何故パンがそんなにお金が必要なのか。 お金が絡む話だけに私も全てを理解しようとして細心の注意を払い、一生懸命彼女の言う事を聞こうとしていたし、また自分の意見も主張した。 その時私が彼女に対して求めていたのは、彼女が必要なお金を私が負担する事を自分自身に納得させるだけの理由であり、彼女が私を納得させる事が出来さえすれば、幾ら必要かという金額自体は決して問題ではなかった。 例えそれがウソでも下らない理由でも自分が納得できればそれで良かったのだが、パンちゃんもそこまで辛抱強くは無かったのかもしれない。 そこに彼女の友達からの電話。 何事も無かったかのように話をする彼女。 タイ語が解る訳ではないが、雰囲気で普通に会話している事くらいは馬鹿でも分かる。 私との込み入った話し合いをしている最中なのに、後で掛け直すと言って切ろうともしない、その倣岸不遜な彼女の態度に元来短気な性格が災いした。 彼女の電話が終わるのを待って、私は仏頂面で言い放った。
"なんだよ! 俺より友達との電話の方が大事なのかよ! 複雑な話してるのに!"
"そんなつもりはないわよ! 別に長話した訳じゃないし…。"
"いつもそうじゃないか、友達との電話を優先して。 一緒に居てもつまらないのか、それとも一緒に居たくないのか? どうなんだよ!"
"貴方、何も解ってくれない…。 貴方とはお金だけで繋がってるんじゃないのに。 どうして私の事を理解しようとしてくれないの、どうしてすぐ怒るの。 信じられない…。"
どうやら女性の話好き・電話好きというのは世界共通らしく、世界中大抵の場所で暇を見つけては友達や恋人と話をしている女性達、特に若い女性達を見受ける事が出来る。 それでも携帯電話が普及する以前はそれほど目立たなかったのかもしれないが、安価に入手できるようになった今となっては一人が二台の携帯を持っていてもおかしくないくらい、携帯電話というのは我々の日常生活に急速に溶け込んできた。 確かに携帯電話は便利なものではあるが、私は今一つ好きになれない。 というのも電源がオンになっていさえすれば、四六時中電話をかけてくる側の都合で時と場所を選ばず呼び出し音に悩まされる事になりかねないからだ。 うるさいと思ったり他人に迷惑だと思ってオフにしておくと、後日連絡を付けたい時に付けられなかった人達から、何故電話を切っていたかと詰問され、こちらからすまないと謝らなければならなかったりするなど、本当に理不尽だと思う。
夜の職業に就いている女性達と自宅で連絡を取り合える幸運な男性達はまず別として、携帯電話の普及によって彼女達との連絡が容易になり、お互いの親密さを深める速度が大幅に短縮された事は有り難い事と思えば良いのだろうか? それとも何かゲームでも行う感覚で恋愛が展開されるようになってしまっているのだろうか? パンちゃんとここまで関係が続けられたのも携帯電話で毎日連絡を取合っていた故であるのに、今はその携帯電話がきっかけとなってお互いの感情が爆発し、引き返せない所まで行ってしまった。 そこで自分が折れて、すまないと言ってやれば喧嘩は単なる痴話喧嘩で終わったのかもしれないが、何も解ってくれない、とまで言われた自分のプライドがそれを許さなかった。 その時に自分が出来た事はそれ以上言葉を続ける事を止める事で彼女をこれ以上傷つけまいとすることだけであった。 おそらく口を開けば彼女を責める言葉しか出てこないであろう事は容易に想像できたからだ。
黙って煙草をふかしている私の背中を、彼女が付けているシャネルNo.5の香りが横切っていき、背中越しに "Thank you for everything、 and Bye-Bye"という彼女の涙声が聞こえて、ドアが重苦しくガチャッと閉まった。 (続く)
第八話 彼女からの手紙
パンちゃんと会わなくなって既に半年以上が経った。 私の隔月ペースの出張は相変わらず続いていたが、あれだけ気まずい別れ方をしただけに、敢えてこちらから彼女に連絡を取るような事はしなかった、というより出来なかったと言ったほうが正しかっただろう。
特に理由が有った訳ではなく、彼女が最後に言った "Thank you for everything,
and Bye-Bye" というフレーズがどうも気に掛かり、電話をしようと思う度にその言葉が頭の中をよぎるので、ついつい躊躇ってしまっている内に時間が過ぎていったという訳だ。
"何が気に掛かるのか"と問われると返答に詰まってしまうのだが、そのフレーズの裏に有った彼女の気持ち等を一つ一つ推測していくと居たたまれない気持ちにされられたからかもしれない。
携帯のメモリーに入っている彼女の電話番号もまだ消去していないし、住所だって知っている。
連絡を取ろうと思えば簡単に取れるはずだった。 そして一言、"あの時はごめんね"と言ってあげる勇気さえあれば二人の関係は、すぐに元に戻ったはずだった、と思う。
結局何も決断できないままずるずると半年が過ぎてしまったのであった。
そんな状態だからその後バンコクへ行っても、ペガサスへは当然の事ながら、所謂連れ出し系の日本人クラブ(タニヤなどのカラオケの類)へは足が向かなくなった。
彼女以上の女の子に巡り会えないだろうという思い込みがあったし、これは万に一つも有り得ないはずだが、その類のカラオケでもしパンちゃんとばったり出くわしてしまったらどんな顔をして会えば良いのか、と考えたら二の足を踏んでしまう。
何も考えずに新しい店で、新しい女の子達と、新しい恋愛ゲームに挑んでいく事ができるような、そんな単純な割切り方ができる性格ではないし、がむしゃらに性欲を満たそうとする歳ではない。
自然、バンコクではせいぜい食事の後に「有馬温泉」でマッサージをしてもらい、抜きたければ近くの「ラ・コスタ」辺りで適当に処理するか、ホテルへ返ってホテトルを呼ぶくらいになってしまい、ナナやパッポンはもとより、ラチャダーなどのお風呂銀座方面へもおっくうで足が向かなくなってしまっていた。
多分、新しく疑似恋愛を始める事を密かに恐れていたのだと思う。
ミレニアム熱も徐々に冷めつつあった頃、オフィスの私の郵送物トレーに会社業務ではないだろうと容易に想像が付く手紙が届いた。
青と赤の縞模様で縁取りされた如何にも国際郵便ですという封筒に、宛先と差出人名をタイプで打った紙を張り付け、そして7Btの切手が二枚。
その差出し人名はタイ語で"綺麗な""可愛い"を意味するパンちゃんの本名だった。
今までも彼女からクリスマスやバレンタイン・デーに手紙やカードを貰った事は有ったので別段驚くという程の事も無かったが、今回違っていたのはその住所であった。
以前書いた通り彼女は母親達と一緒にバンコク・ノーイに住んでいるはずなのに、そこには私が聞いた事の無いUttaraditという地名が記されていた。
地図で調べるとバンコクの北西チェンライの方向で、約400km強離れている。
バンコクとチェンライの丁度中間地点くらいでスコタイの近くの町であった。
そして名字も私の知っている彼女の本名とは似ているが違っていた。 それを見た瞬間、私は彼女が結婚でもして他の場所へ移り住み、今では幸せに暮らしていますとでも書いて寄越したのかと勝手な推測を巡らせた。
よくよく考えれば非常に自分勝手な、都合の良い解釈を思い付くものだな、と自分自身に失笑してしまうのだが。
|
親愛なる△△△へ、 |
彼女の手紙を読み終えた後も、二回三回と読み直した。 そして嬉しい気持ち、もう一度会いたいと思う気持ち、自分を恥じる気持ちなどが次から次へと交錯して、最後には居たたまれない気持ちで一杯になった。
翌日、一日置いて気持ちの昂ぶりがやや収まってきた私は、おもむろにパソコンに向かって
"Dear Pan-chan、"と打ち込み始めていた。 (続く)
第九話 熱い思い
そうは言うものの彼女への返信はすぐに出した。 おそらく彼女の元へ届くのが一週間くらい掛かるし、彼女が返事を書いて送り返してくるのには今から一ヶ月ほどは掛かるだろう、そう思っていた。 だがそれで良いと思っていた。 電話を使ってリアルタイムのやり取りも楽しいかもしれないが、敢えて時代に逆行する形でゆっくりとお互いの気持ちを整理して、自分の言葉で自分の気持ちを文字にする事でもっと何かが解るかもしれない、そう思えた。 もし今自分が後十年若かったらセックスへの興味が先に立ち、パンちゃんの感情を無視してでも再度肉体関係を持つ事に腐心していたかもしれない。 セックスを快楽追求の手段としてのみ認識し、セックス本来の目的・意味等は考えもしなかったのだろうと思う。 自分の経験から言えば、若さに裏打ちされた自信は往々にして過信を生み、理由も判然としないまま結果としてお互いを傷付ける事になる。 わたしは花火のような激しさ・瞬間の快楽より柔らかなゆったりとした道を選んだ。 そして一ヶ月が過ぎていった…。
| 親愛なる△△△へ、 手紙有り難う! 貴方の変わらない優しさと愛情に感謝します。 (貴方からの手紙をもらって)元気付けられた気がします。 そう、また(会社で)偉くなったのですね、 私も嬉しく思います。 忙しい中でも返事を書いてくれて本当に有り難う。 でもまだ私からの説明が不十分だったようですから、説明させて下さいね。 自分で書けば良かったのだけれど、あの手紙は私がタイ語で書いたものを友達に頼んで英訳して貰った上ワープロで打ってもらったものです。 ごめんなさいね。 そうですね、しばらく手紙を交換し続けるというのは私も良い考えだと思います。 でも問題なのは、手紙を書くという事は私にはとても時間が掛かる事だという事です。 ですから、本当は貴方が電話してくれたなら一番望ましい事なのですけれども…。 そう、色んな事を早く伝える為には(電話が)一番良い方法だと思いますよ。 あ、でも駄目ね、元はと言えば電話がきっかけとなって全てが崩れていってしまったんですものね。 私って馬鹿ね。 別に私の家族に何か起きたとか、そういう事は有りません。 手紙に書いてあった私の名字も友達のタイプミスです。 △△△、本当に手紙を書いてくれて有り難う。 確かに貴方の手紙は難しいけれども(注:我々が普通に使う英語のイディオムなども彼女達には時折難しく受け取られるらしい)、大丈夫です。 今、この手紙をバンコクのおねえさんに会いに出掛ける前にウタラジットで書いています。 お願いです、タイに来る事があったら直ぐにでも電話して下さい。 そしてバンコクで貴方に会えれば良いと心から祈っています。 もう出掛けなければいけません。 すぐに貴方からの返事がくることを期待しています。では健康に気を付けて、お仕事頑張って下さい。 Always Love PAN 01-8XX-XXXX |
既に迷う事は何も無かった。 彼女に返事を出した後色々と考えてみたけれども、やはり次回は電話で連絡を取合い、もしお互いの都合が合えば一度会って話し合ってみようという気持ちになっていた。 家内にはかなり疑われたが、いずれにせよ顧客と当方のスケジューリングの都合で99年のクリスマスイブを挟んでのバンコク出張が決定していた私は、この二度目の手紙を読み終えた瞬間にパンちゃんの携帯電話に連絡を入れた。 (続く)
第十話 再会
話はパンちゃんからの二度目の手紙を受け取った時点へ戻る。 既に意を決していた私は迷わずパンちゃんの携帯の番号を押して、七ヶ月振りくらいに彼女の声を聞いてみる事にした。
"アロー…、アロー?"
"Hello、パンちゃん? △△△です。"
"えーっ!! 本当?! 本当に△△△なの?"
"今日パンちゃんからの手紙着いたよ、有り難う。 迷ったけど電話しました。"
"嬉しーいっ! 電話かかって来るとは思わなかったから…。"
"こっちこそまたパンちゃんと話出来て嬉しいよ。 そうそう、実はクリスマスの時期に出張でバンコクに行くんだけど、ウタラジットからバンコクに出てこれるかな?"
"えっ、本当に会えるの?! もちろん大丈夫よ! でもクリスマスっていったらもうすぐじゃない。 …本当にバンコクに来るのね、とても楽しみにしているわ。"
"そうだね、ホテルはいつもの所だから、バンコクに着いたら電話するよ。 御飯でも一緒に食べよう。"
クリスマスを明後日に控えた常宿は、いつもと違った趣を見せている。サトーン通りから奥まった所にある本館へと続く道の両脇は、背の低い植え込み其々に黄色や緑、赤といった透明感のある様々な色のイルミネーションが施され、頭上の木々にはチューブに入った電飾が掛け渡されて何か幻想的な雰囲気さえ漂わせている。 夜のディズニーランドに雰囲気が似ていない事も無い。 この風景だけ見せられたらこれがバンコクであるとは俄かには信じ難いかもしれない。 私は受付近くのラウンジでコーヒーを飲みながら、彼女が現れるのを待っていたが、"いつも通り"彼女は遅刻してきていた。 だが待つ事に慣れてしまっているし、今日は何故か待つ事が全く苦にならない。 そんな事を考えている間に、彼女が乗ったタクシーが玄関に到着した。
黒の薄手のワンピースにショールをかけた彼女は以前と全く変わっていなかった。 その大きな瞳は私をじっと見詰めて動かず、嫌が応にも視界に飛び込んでくるその程よく膨らんだ胸元も八ヶ月というブランクを忘れ去せるに余りある程魅力的だった。 彼女を抱きしめたい衝動に駈られたが、久し振りに会った事で躊躇いを禁じ得ず、行動を起こす事が出来なかった。 そして余りにも強く会いたいと思っていると、実際会った時にむしろ言葉が出てこないものだという事もその時初めて知った。 お互いを見詰め合っているだけで会話している気分になり、言葉が出てこないのだ。 大きな瞳に笑みを湛えている彼女に対し、愚かにも私が最初に放った言葉は"どこに御飯食べに行こうか"であった。 もっと格好良い言葉や甘い言葉などが出ても可笑しくないほどに、舞台設定は整っていたというのに…。 幸いな事に彼女も多少なりとも舞い上がっていたようで別段気にする風でもなく、"どこでもいいけど…、そうね静かな所が良いわね。 川を眺めながらっていうのはどうかしら?"と返してきた。 "じゃあ「シャングリラホテル」の「サラティップ」でも行こうか"という提案に彼女はにっこりと頷いた。 イルミネーションの煌く中、私とパンちゃんはタクシーへと乗り込み、チャオプラヤ川沿いの「シャングリラホテル」へと向かった。 手を繋いで横に座っている彼女からは、懐かしい香りであるシャネルNo.5が漂い、彼女の存在を実感させた。 (続く)
第十一話 クリスマス・ファンタジー
クリスマスイブを明日に控えているとはいうものの、バンコクではまだまだ暖かく、川面を吹きぬけていく風が気持ち良いくらいに感じられる。 「サラティップ」のオープンタイプのテーブル席に陣取り、パンちゃんと私はシンハで乾杯した。 時刻は8時近い。 テーブルの上に置かれたキャンドルに照らし出された彼女の横顔は、はっきりとした顔立ちと相俟ってエキゾチックでさえある。 いいオンナだな、改めてそう思った。言葉の障害があってもお互いの気持ちが通じ合えば、恋愛は可能だ。 先人の"恋愛は障害が多いほど燃え上がる"という言葉が思い出される。
私と喧嘩した後の彼女は、酒を飲んで自分の感情を誤魔化しつつ客に身体を任せるという行為に疑問を抱き始めたそうだ。 不特定多数の男性の相手をするという事を楽しんでできる女性達は別として、その精神的苦痛は計り知れないものがある。 昔読んだノンフィクションの中でソープに勤める女性が"この商売、本当に好きな人がいたら出来ないよ。"と語っていたのを思い出す。 一旦沸き上がった疑問は小さくなる事はなく、次第ペガサスも休みがちになり、ついには辞めてしまったそうだ。 そして訪れたのは彼女が最も恐れていた、普通の友達が誰もいない、というシチュエーション。 母親の店の手伝いをしてみたりしたが、バンコクにいる限り昔の悪い友達からの連絡がひっきりなしにあるし、また大都市にありがちな拝金主義的な雰囲気、そういった諸々の事から、いや人間達から逃げ出したかった、ということらしい。 結局母親と話し合い、叔母が住んでいるウタラジットへ引っ越して、新しい生活を始めてみようという事になったとの事だ。 バンコクノーイの家には二人の姉が引き続き住み、ウタラジットへは母親と弟と自分が叔母の家の近所に借家を見つけて引越し、そこで小さな食堂を開いてパンちゃんも店の看板娘として朝から晩まで働いている。 シンプルな生活で、バンコクにいた時のような生活の変化は全く無いけど、でもとても落ち着いた気分だ、と彼女は言った。
からかい半分で
"彼氏は?"と聞くと伏し目がちになり一言、
"…今はいないわ…。"と返ってきた。
"でも君に言い寄ってくる奴等は沢山いるだろう"と意地悪な質問を更に続けると、多少むっとした表情を見せながら
"だって…、既に好きな人がいるのに、何をしろっていうのよっ!"と怒られた。 全てを知っている上でわざと意地悪な質問を繰り返して相手の反応を楽しむ、私の悪い癖かもしれない。 すかさず彼女の頬を撫でてやりながら
"ごめんね"と謝った。 その手の甲に軽くキスをして、
"貴方の事もね、忘れられるかもしれない、そう思ってウタラジットへ行ってみたのだけれど、それだけは出来なかった。 確かにウタラジットにいると、ペガサスの事やお酒や薬の事なんか全部忘れる事ができるわ。 でも貴方は…、忘れるにはその存在が大きくなり過ぎていたみたい。 思い出すのは貴方との事ばかり。" と言って彼女はイルミネーションで飾り付けられているホテルの方を見上げた。
"本当にこうして貴方とまた会えるなんて思わなかったわ。 私を忘れないでいてくれて有り難う…。 ねぇもう少し飲みましょうか。" そう言いながらシンハの入ったグラスを持ち上げ乾杯を促す彼女へ、こちらもグラスを持ち上げて応える。 自分のグラスを飲み干してから、いつウタラジットへ帰るのか聞くと、今回は私に会いに来ただけだから明日にはバスに乗って帰ると言う。 何でも片道6時間ほどかかると言っていた。
「ありがとう」、そう心の中で呟いた。
食事を終えた我々は真っ直ぐサトーンの常宿へと戻ることにした。 どこかに寄り道する気分ではなかったし、早く二人きりになりたかった。 敢えて彼女に何も聞かず、半ば強引にホテルへ帰る旨を告げると黙って腕を組んでついてきた。 さっきテーブル越しに会話をしていた時は次から次へと出てきた言葉がまた途絶えている。 約八ヶ月の間に起こった事をたったの二時間やそこらで咀嚼しようとしたことから起きている沈黙だった。 将棋に例えて言うなら、相手の置いた駒に対して数手先のバリュエーションを考え、次に自分が打つべき手を考えている、そんな所だろうか。 しかし決して居心地の悪い沈黙ではなく、繋いだ手から伝わる彼女の温もりを確かめているだけで充分だった。 お互いに殆ど無言のまま、タクシーはイルミネーションの煌くエントランスを通り抜け正面玄関へと到着した。
以前そうしていたように、まるであの時から何事も無かったごとく、ごく自然に我々はセックスした。 シャワーの後、生まれたままの姿でどちらからともなく抱き合い、お互いを愛撫し、そして私は彼女の中に果てた。 弾力のある乳房は相変わらず掌に質感をもって応えたし、彼女自身の部分も私の愛撫に素直に反応した。 以前と違う事が一つ有るとすれば、お互いに殆ど素面でセックスをしたということだろう。 当時は何かを忘れようとする為なのか、"浴びるほど"という言葉が適切なくらい、アルコールを摂取しないと彼女はセックスしなかった。 アルコールが入ればある部分は敏感になり、ある部分では鈍感になる。 それが彼女との激しいセックスの原因だったかもしれない、今はそう思える。 だが今日は、以前必ず嗜んでいたセックスの後の一服をする気配がなく、また急いでシャワーを浴びようとする気配もなく、彼女は私の胸に顔を埋めて余韻を楽しんでいるかのようだ。 簡素な生活環境に置かれるとセックスが最大の娯楽となる事は、タイやフィリピンなどでは子沢山であることが証明しているし、中国の少子化政策は逆の意味でそれを証明している。 おそらく彼女にとっても最近は"我を忘れて"楽しめる事が無かったのだろう、という事が推測できる。 私が二本目の煙草を吸い終え灰皿でもみ消した時、ふいに彼女が私の目を見詰めて、"△△△、パンちゃん、うれしい!"と日本語で言った。
クリスマスだから厨房で働くお母さんの為に新しいキッチン用品を買っていってあげたい、と言っていた。 自分で買ってあげたい、その位のお小遣いは持っている、と言い張る彼女に、お店が忙しいのに無理矢理休ませたペナルティだ、と言い聞かせて笑いながら5,000Btほどバッグの中に突っ込んだ。 "コップン・マーク・カー…"、済まなそうな表情を見せながら彼女が呟く。 田舎の食堂で働く彼女が"真面目に"働いていると仮定すれば、彼女がもっているというお小遣いの金額はたかが知れている。 人間は一度余裕のある生活、所謂"一段上の生活レベル"を味わってしまうと、その生活レベルを下げる事は大変な努力と苦痛を伴う。 ウタラジットにいれば周りからの誘惑は少ないかもしれないが、此処は大都市バンコクである。 お金さえあれば欲しいものは何でも手に入る場所だ。 お母さんの為だけでなく、自分でも欲しいものがあるだろう、そう思って無理矢理掴ませた。 それが彼女にとって良い事か悪い事なのか、それはこの後彼女が自分で判断していくだろうし、もし彼女がそういった"イージーマネー"の魅力に再び取り付かれたなら、かなりの確率で彼女はバンコクに舞い戻り以前と同じような仕事を再び始める事になるはずだ。 しかしその時の私の一人よがりの考えでは、今この時点で彼女にとって一番空しい事は欲しいものがあるのにお金が足りなくて買えない、という事ではないかと思った。 6時間もかかるのであればそう頻繁にはバンコクに出てくる事も叶わず、たまに出てきたのなら、したい事や欲しいもの等がそれなりに有るはずだ、そう思ったのだ。 まあおせっかいな"足長おじさん"といったところか。
傍らで微かな寝息を立てながら寝入ってしまったパンちゃんの頬にキスをして、彼女の温もりを確かめるように軽く抱きしめがら、"…メリークリスマス…"と呟いた。
時計はとっくに12時を回ってクリスマスイブになっており、"なんか安っぽいテレビドラマみたいなシチュエーションだな"と一人思いつつ、私も眠りに落ちていった。 (続く)
最終話 それから

実はパンちゃんと会ったのは11話で書いた去年のクリスマスイブが最後でした。 セックスの後お互い爆睡してしまい、翌朝彼女が慌ただしく部屋を出ていくのを見送ったのが、結局最後になっています。 その後は彼女からの手紙も電話もありませんし、こちらからも敢えて連絡をとっていません。 音信不通という事ではなく、バンコクノーイとウタラジットの住所も持っていますし、携帯の電話番号だってまだメモリーに入っています。 また、私がバンコクに行かなくなったという事でも有りません。 相変わらず隔月ペースでの出張は続いています。 ですから彼女と会おうと努力すればそれは実現可能な事だと思います。
ただ彼女が、その理由が何であれ私に連絡を取らないという事は、私を必要としなくなったという事かもしれないし、私に会いたいと思わないのであるなら、そっとしておいてあげたい、と思っています。 私と一緒になるより、タイ人の歳相応の男性と知り合って一緒になった方が幸せになれるに決まっています。 だって私は家族も居るし、タイ語も話せないのですから…。 物質的な豊かさだけでは幸せになれないし、逆に精神的な豊かさだけでも現代社会では幸せな生活は出来ません。 両方がある程度のバランスを持って存在しないと、穏やかな気持ちには成れないのでしょうね、人間は欲の固まりですから。 だから彼女からの連絡が無いという事は、彼女が今は穏やかな暮らしを幸せに営んでいる、そう思いたいですね。
今までに、個人的な付き合いをした素敵な女性達は沢山いますが、タイの女性はパンちゃんが最初で最後で、当然今でも私の心の中でも飛びっきりの思い出になっています。 多分死ぬまで忘れない女性の一人になるでしょう。 私もサラリーマンですから、いつかは転勤で現在の仕事を離れ、タイとは縁が薄くなる可能性があります。 でも出張ベースのサラリーマンでもこんなに素敵な恋愛(すみません、自分で言っちゃいけませんね)ができるんですよ、という事を皆さんに知って頂ければ『パンちゃん物語』の役目は果たせたかな、と思います。
こんな事を書いたら人によっては反感を持たれる事は百も承知の上で、私から皆様への助言をさせて頂き最後のご挨拶の代わりとさせて頂きます。 また何かの形で皆様の前に登場させて頂く事がありましたら、何卒宜しくお願い致します。Neguro
《Neguroからの助言》私が今まで経験した事から学んだ教訓です。 皆さんにも素敵な恋が訪れる事をお祈りします。
1. 外人だから…、風俗で働いているから…、という偏見で他人を見下すのは止めましょう。 必ず何らかの形でトラブルの元凶になり、後日自分に跳ね返ってきます。 形態はどうあれ、彼女達が提供してくれるのは貴方を心地よくさせてくれる"サービス"だという事は忘れずに、彼女達が気持ち良くサービスできる雰囲気を作り出してあげて下さい。
2. 女性達が満足するのは貴方のベッドテクニックや優しさではなく、まずお金です。 初対面ではそれしか信じられるものが無いから。 値段交渉はキチンとしましょう。 もし自分の語学力に自信が無いなら海外で遊ぶのは無謀だし、曖昧な交渉をして後で嫌な思いをするのは結局自分ですから。 貴方を素敵だと思えば、彼女達の方からまた会いたいと言ってくるはずです。
3. 自分は金を払う『客』だからホステスに何をしてもいいだろうという態度は禁物です。 アジア中どの国の風俗でもこの手の態度を取る客に女の子は絶対心を開きませんし、オフしたとしてもマグロ確定でしょう。 「あいつは急速冷凍マグロになった」と不平をこぼす前に、自分に原因が無かったかどうか考えてみるとまた違った遊び方が見えてくるのではないでしょうか。